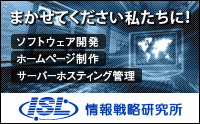信州の偉人
小林一茶 江戸を代表する俳諧師
小林一茶という人物
ここでは様々な視点から、小林一茶の人物像に迫ります。
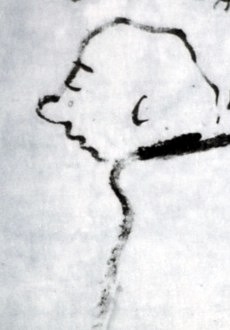
|
|
ここで、一茶の遺した俳句をいくつか紹介します。
一茶の詠んだ俳句から、一茶の人柄を感じてみてください。
![]()
初夢の中に故郷の町が出てきて、込み上げてくるものがあった。
季節:新年 季語:初夢
![]()
道に遊んでいる雀の子よ、そこを早くのけよ。お馬が通るからあぶないぞ。
季節:春 季語:雀
![]()
あれあのように蝿が手足を合わせて命乞いをしているじゃないか。かわいそうだから打たないでやっておくれ。
季節:夏 季語:蝿
![]()
親のない子供の雀よ、私も親のない寂しさはおまえと同じだ。こっちへ来て、一緒に遊ぼうじゃないか。
季節:春 季語:雀
![]()
カエルがけんかをしている。やせたカエルよ、がんばれ負けるな、おれ(一茶)がここについているぞ。
季節:夏 季語:蛙
![]()
畑で大根を引き抜いている人に道を尋ねたら、今抜いたばかりの大根で道を指して示してくれた。
季節:冬 季語:大根引き
![]()
お上の大名はにわか雨に濡れながら道を通っているが、こっちの下の者は炬燵に入ってそれを見物しているよ。
季節:冬 季語:炬燵
![]()
あれこれ考えたところでどうにもならない。この年の暮れも、総てを仏様にお任せするよりほかにない。
季節:冬 季語:年の暮
![]()
名月を取ってくれとわが子が泣いてねだる。親として、それに応えてやれないじれったさと子供のかわいらしさ。
季節:秋 季語:名月
![]()
この世は露のように儚いものだとよく知ってはいても、それでもやはり愛しい我が子の死はあきらめきれない。
季節:秋 季語:露
![]()
秋風が吹くころになった。あの赤い花は、死んだ「さと」が大好きで、いつもむしりたがった花だよ。
季節:秋 季語:秋風
![]()
目の前の狭くて小さい障子にあいた穴から拡がる天の川のなんと美しいことか。
季節:秋 季語:天の川
![]()
桜は一夜のうちにささら、ほさらと散っていってしまうんだなぁ。
季節:春 季語:桜
![]()
ああ、また今日も忘れ物をした、と家までの道を日陰を選んで戻っていくよ。
季節:夏 季語:日陰
小林一茶の生涯
ここでは小林一茶の生涯を紹介しています。
| 年号 | 年齢 | 出来事 |
|---|---|---|
| 1763 | 0 | 北信濃柏原村で農家の長男として生まれる |
| 1765 | 2 | 母が逝去 |
| 1770 | 7 | 継母ができる |
| 1777 | 14 | 継母に馴染めず江戸に奉公に出される |
| 1792 | 29 | 江戸で俳諧に目覚め、14年後故郷に帰る |
| 1793 | 30 | 京阪神・四国・九州を俳諧の修行のため6年間歴遊 |
| 1802 | 39 | 父の危篤で帰郷するが逝去してしまう |
| 1813 | 50 | 遺産相続問題が解決し、故郷に帰る |
| 1815 | 52 | 22歳年下のきくと結婚 |
| 1819 | 56 | 長女が亡くなる |
| 1828 | 65 | 火事で家を失い、焼け残った土蔵で生涯を終える |
幸福とは言えない子供時代
小林一茶は江戸時代、現在の長野県上水内郡信濃町大字柏原に弥五兵衛の長男として生まれる。
本名は弥太郎といった。母・くには一茶が2歳のときに逝去してしまい、7歳の時に継母・はつを迎える。
やがて義弟・仙六が生まれると、お守りをやらされ、弟が泣く度にわざと泣かせたと、父母に杖で打たれること
「日に百度、月に八千度」(父の終焉日記)だったそうだ。13歳のとき唯一の味方であった祖母が亡くなると、
継母と不仲であった一茶は江戸に出されることになる。
俳諧の世界に目覚める
故郷を出されたあとの一茶の消息はほとんど伝わっていないが、江戸で一茶は俳諧の世界に目覚めていった。
25歳のとき二六庵小林竹阿に師事していたとも言われている。29歳のとき俳諧師として芽が出始めていた一茶は
14年ぶりに故郷に帰り、翌年からは俳諧の見聞を広めるため6年にも渡って京阪神・四国・九州を旅している。
このころ「たびしうゐ」や「さらば笠」を出した。
父の死と遺産相続争い
一茶が再び故郷に戻るのは39歳のときで、父は重病で倒れており、最期を看取ることとなった。
父は「財産を一茶と弟たちで二分するように」と遺言を残すが、継母と弟たちが一茶に財産を分配することに
反対したため、遺産相続問題は12年もの間続くことになる。一茶は父が亡くなる前後のことや、この争いの様子を
「父の終焉日記」に記録している。一茶は江戸で俳諧の宗匠を務めつつ、継母たちと戦い、50歳のとき和解に至った。
結婚と重なる不幸、終焉
遺産を分配された一茶はやっと長野に戻ることができ、その2年後、28歳のきくと結婚する。
二人の間には4人の子供が生まれたが、いずれも幼くして亡くしてしまう。さらに追い討ちをかける様に
妻・きくも痛風で逝去する。その後、再婚するが三ヶ月で離縁となり、再々婚で3番目の妻・やをと一緒になった。
しばらくの平穏を得るが、今度は火事により家が消失してしまう。焼け残った土蔵を仮住まいとするが、
持病の発作により、そのまま一茶は65歳で逝去した。翌年、やをが一茶の子を産み、後に一茶家を継ぐこととなる。
血は絶えなかったものの、一茶はついに我が子の成長を見守ることはできなかった。
小林一茶の残した名言
ここでは小林一茶の印象に残った名言を紹介します。
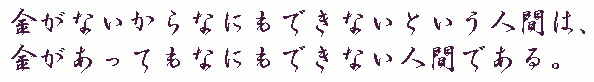
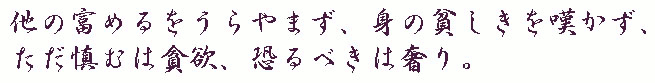
一茶の生活はかなり貧乏なものだったようだ。
一茶は俳句の中で、自身の生活の様子をいくつか謡っている。
![]()
どうひいき目に見ても、自分の姿は寒そうでみすぼらしいことだ。
![]()
家の裏壁に、雪がしがみつくようにべったりとくっついている。家がみすぼらしいので、
雪までもが貧乏くさく見えることだ。
![]()
わが家の庭にも春が来て梅の香りがただよっている。
しかし、こんな貧乏暮らしでは誰が来ても欠け茶碗しか出すことができない。
確かに、貧乏そうだ。
しかし、悲劇の中にありながら楽しんでいるようにも感じられる俳句もある。
![]()
焼け跡の土はまだ温かく、家に住みついていた蚤が騒いでいるようだ。という意味。
これは火事によって家が燃え落ちてしまったときにできた俳句である。
本当に楽しんでいるのか、自分の不運に開き直っているのかは定かではないが、
あまり悲観して塞ぎ込んでいた様子は伺えない。
このような貧乏な生活の中にありながらも、一茶はそれを理由にやりたいことができないと嘆いたりはしなかったということだ。
これは一茶の経験から得た言葉というよりは、常に自分に言い聞かせていた言葉のように感じる。
コメントの投稿
トラックバックURL
http://www.isl.ne.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1514